計測・測定機器管理台帳&点検表の作り方と運用ポイントを徹底解説【無料Excelテンプレート付き】
更新日:
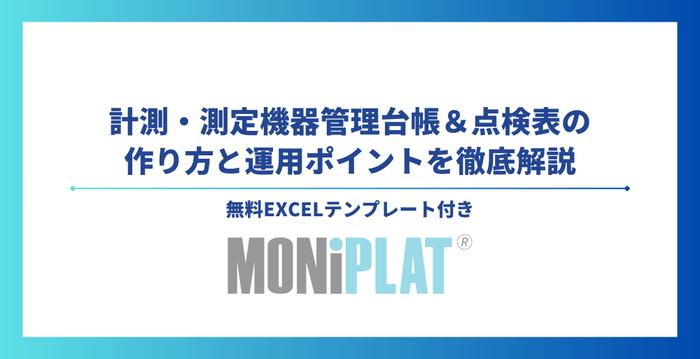
計測機器の点検管理はどこまでやればいいの?や、台帳や点検表にどのような項目を入れればいいの?といった疑問を抱えながら、日々の点検管理に頭を悩ませている現場担当の方も多いのではないでしょうか。
計測機器は製品の品質や安全性に直結する重要な機器です。その一方で、管理方法が属人化していたり、点検記録が曖昧だったりした場合、いざという時にトラブルや不良品の原因を突き止められないというリスクもあります。だからこそ、台帳や点検表による適切な記録管理は、品質保証体制の第一歩として非常に重要です。
本記事では、計測機器の管理業務に必要な考え方から、実際の台帳・点検表の作成方法、運用のポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説しています。さらに、点検業務ですぐに使える無料のExcelテンプレートもご用意しているので、まずはできるところから取り組んでみてください。
計測・測定機器の管理台帳とは?目的や機器の種類について解説
製造・品質管理の現場では、測る行為が製品の合否や安全性を左右します。そのため、計測・測定機器は単なる道具ではなく、品質保証の根幹を支える管理対象とされています。
この章では、計測・測定機器の基本情報から、管理台帳の必要性、国際規格ISO9001との関係性について、実務目線でわかりやすく解説します。
そもそも計測・測定機器とは?製造現場で使われる主な種類を紹介
計測・測定機器とは、温度・長さ・圧力・重量・電流など物理的な量を数値化する装置の総称です。特に製造業や品質管理において、製品の精度や工程の安定性を担保するうえで欠かせない存在です。
下記に代表的な測定機器とその測定対象・用途をまとめました。用途が重複する機器や現場では不要な高度機器は削除しています。
| 種類 | 測定対象 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 温度計・温湿度計 | 温度・湿度 | 工場・倉庫内の温湿度管理、工程環境の監視 |
| 圧力計 | 圧力 | 配管・タンクの圧力監視、安全装置の作動確認 |
| 流量計 | 流体の流れ | 液体や気体の流量制御、バルブの管理 |
| 騒音計 | 音圧レベル | 工場や建設現場の騒音測定、環境基準対応 |
| ノギス | 外径・内径・深さなど | 製品寸法のチェック、加工品の検査 |
| マイクロメーター | 微小寸法(μm単位) | 部品の厚さ、直径の高精度測定 |
| ダイヤルゲージ | 寸法の変化・変位 | 平面度、真直度、振れの測定 |
| レーザートラッカー | 大型の対象物の大きさ | 大きな部品や構造物の測定 |
| 三次元測定機 | XYZ方向の立体寸法 | 金型・機械部品の高精度測定・品質保証 |
| トルクレンチ(トルク計) | 締め付けトルク | ネジやボルトの締付力の管理 |
| デジタルマルチメーター | 電圧・電流・抵抗など | 電子回路や装置の電気的確認 |
現場で実際に使用されている機器に合わせて、上記をカスタマイズした管理が必要です。
計測・測定機器管理台帳とは?ISO9001との関係性と管理の必要性
計測・測定機器管理台帳とは、機器の固有情報や点検・校正・使用履歴を一元的に記録する台帳です。品質管理において、機器が正しく測れている状態であることを証明できなければ、測定値そのものの信頼性が問われ、製品や工程全体の品質保証に支障が出る恐れがあります。
そのため、下記のような目的で管理台帳が活用されます。
- 品質保証体制の構築:設備や機器の性能が常に適正であることを社内外に示すため
- トレーサビリティの確保:製品不具合が起きた際「どの機器で、いつ、どのような状態で」測定されたかを追跡するため
- 監査・法令対応:品質マネジメントシステムでは、校正履歴や管理状況の記録が要求されるため
また、ISO9001では以下のような管理要求があります。
適切な監視および測定機器が識別され、校正または検証されており、使用に際して適切な状態にあること
つまり、管理台帳はISO9001対応の「証拠」となる重要なドキュメントであり、点検・校正記録や担当者の管理状況も含めて精度高く運用する必要があります。
出典:[ 経済産業省 / 計量標準FAQ ]
まとめ
計測機器は品質保証の根幹を支える重要設備であり、管理台帳で固有情報や履歴を一元化することがISO9001対応やトレーサビリティ確保に直結します。
「点検」と「校正」それぞれの目的の違いを理解しておこう
測定機器の管理において、「点検」と「校正」はまったく異なる目的を持つ重要な作業です。どちらか一方では不十分で、両方を適切に組み合わせることで、機器の信頼性と測定精度が維持されます。
この章では、それぞれの定義・目的・実務上のポイントを明確に整理して解説します。
点検とは?日常的に行う状態確認と予防保全
測定機器の管理における点検とは、測定機器が故障していないか、正常に作動しているかを確認する作業です。日々の使用前・使用後に、目視や簡易動作で以下のような項目を確認します。
- 電源が正常に入るか
- 表示や操作反応に異常がないか
- 外装やセンサー部に傷・破損・汚れがないか
- 既知の標準物と照らして極端な誤差が出ていないか
点検はメンテナンスや異常の早期発見を目的としており、一般的には現場の担当者が実施します。異常があれば、クリーニングや電池交換、軽微な修理などの対応を行います。
また、点検はあくまで「壊れていないか」の確認であり、「測定値の正確性」を保証するものではありません。
校正とは?測定値の正しさを保証するための精密作業
測定機器の管理における校正とは、測定機器が正しい数値を示しているかどうかを検証する工程です。基準となる標準器が表示する値と比較し、許容誤差の範囲内かどうかを判断します。具体的には、以下の手順通りに実施します。
- 標準器(トレーサブルな基準)で基準値を取得
- 該当機器の測定値と比較
- 許容誤差を超えていれば再調整や修理を実施
また、校正は精密かつ専門的な作業であるため、以下のような管理が求められます。
- 認定機関または社内で訓練を受けた校正員が実施していること
- 使用した標準器が国家標準にトレーサブルであること
- 校正手順が文書化されており、再現性があること
- 校正記録・証明書が正しく保管されていること
これらを満たすことで、校正作業は「有効な校正」と認定され、校正証明書が発行されます。
なぜ「点検」と「校正」どちらも必要なのか?
点検と校正の違いを整理すると以下のようになります。
| 項目 | 点検 | 校正 |
|---|---|---|
| 目的 | 故障・異常の有無を確認 | 測定値の正確性を検証 |
| 実施者 | 主に現場担当者 | 認定技術者・外部校正機関 |
| 頻度 | 日常または定期的 | 年1回程度が目安(機器による) |
| 方法 | 目視・動作確認 | 標準器との比較測定 |
| 記録 | 点検表に記録 | 校正記録+校正証明書 |
点検だけでは壊れていないことは分かっても、正しい値を出しているかは分かりません。逆に、校正済みでも日常点検を怠れば、落下や破損で測定異常が起きるリスクがあります。
そのため「点検=日々の安全確認」と「校正=精度の保証」として、両方を計画的に実施することが測定機器の信頼性維持に不可欠なのです。
ちなみに、校正周期は法的に定められていない場合も多いです。そのため、測定値の変動リスクが高い機器であれば、半年から年1回の校正が望ましく、使用頻度が低く環境変化も少ない機器であれば、年1回程度で管理できます。使用頻度や重要度、過去の誤差傾向をもとに適切な周期を設計しましょう。
まとめ
点検は日常的な動作・外観確認で異常を防ぎ、校正は測定値の正確性を保証します。両方を計画的に組み合わせることで設備機器の信頼性を維持できます。
計測・測定機器管理台帳&点検表を作成するメリットとは?
計測機器の点検表や管理台帳を運用することで、品質維持や業務効率化など、さまざまなメリットが得られます。この章では、代表的な5つの効果について詳しく解説します。
測定の正確性と製品品質を維持できる
点検表・台帳を定期的に更新することで、測定機器の誤差や不具合を早期に把握でき、測定精度の劣化を防げます。結果的に、製品の加工精度や検査結果の信頼性に直結します。
測定機器の不具合による誤った合格判定や精度不良による再加工・再検査を防ぐことができ、不良品の流出リスクや顧客トラブルも最小限に抑えることが可能です。
トレーサビリティを確保し、原因調査を迅速化できる
万が一、製品不具合やクレームが発生した際も「どの機器で、いつ、どのような状態」で測定されたのかが記録されていれば、原因調査が迅速に進みます。
測定の履歴が残っていない場合、調査は推測や関係者ヒアリングに頼らざるを得ず、結果として対応が遅れ、顧客満足度や社内信頼にも影響を及ぼしかねません。
点検・校正スケジュールを見える化できる
管理台帳によって、各機器の校正周期や次回点検日が一元的に把握できるようになります。属人化しやすい、いつ誰が何を点検すべきかという作業が標準化され、担当者の作業負担も軽減されます。
スケジュールの可視化によって点検漏れを防ぎ、計画的な保守体制の構築にもつながります。
突発的な故障やトラブルを予防し、コストを削減できる
点検を怠った機器は思わぬタイミングで故障し、ライン停止や緊急対応に発展することも少なくありません。定期的に状態を確認して異常の兆候を早期に把握することで、予防保全が可能になります。
結果として、突発的な修理費や生産ロスを回避でき、コスト削減という観点からもメリットが大きい施策です。
ISO9001や監査対応における信頼の証拠になる
ISO9001などの品質マネジメント規格では、測定機器の管理と校正記録の保管が求められます。適切に点検表や台帳を用いて管理することで、第三者監査の場面でも明確なエビデンスとして提示できます。
また社内だけでなく、顧客や取引先に対しても、品質管理が整備されている企業であることを示す信頼材料となります。
まとめ
点検表・管理台帳を活用することで、測定精度や品質維持、トレーサビリティ確保、コスト削減、ISO対応など、多方面で効果を発揮して信頼性の高い運用を支えます。
計測・測定機器管理台帳&点検表の作成方法を解説
この章では、実際にどのような項目を計測機器の管理台帳・点検表に記録すべきか、そしてそれらをどのように設計・活用するべきか具体的に解説します。テンプレートやExcelを活用する場合にも応用しやすい内容です。
計測・測定機器管理台帳に記録すべき主な基本情報と構成
計測機器の管理台帳は「どの機器が、どのような状態で、誰の管理下にあるのか」を明確にする機器の個別管理シートです。以下の項目を含めることで、トレーサビリティと保守性が確保されます。
| 項目 | 目的 |
|---|---|
| 管理番号 |
|
| 機器名・メーカー名 | 一般名称だけでなく正式名称・製造元を明記することで、外部委託時や部品手配時にもスムーズに連携可能 |
| 型式・製造番号 |
|
| 購入日・使用開始日 |
|
| 保管場所・使用場所 | 使用環境の特定により、故障原因や精度への影響要因(温湿度・振動等)の要因分析にも |
| 管理担当者 |
|
| 校正周期・最終校正日 |
|
| 校正結果(誤差など) | 校正結果が記録されていれば、経年変化や性能劣化の傾向も分析可能 |
| 校正証明書の有無・保管場所 | 証明書の有無を記録し、紙・PDFの所在を明確にしておくことで、監査対応や顧客提出にも即対応可能 |
管理台帳を設計する際には、基本情報を左側に固定し、右側に校正・修理履歴などを時系列で追加していくレイアウトが、実務上もっとも運用しやすい形式です。このレイアウトであれば、機器の状態をひと目で把握することができ、過去の履歴も横に追いやすくなります。
また、入力ミスや記入漏れを防ぐために、担当者名や使用場所などは選択式(プルダウン)で入力できるようにしておくと効果的です。これによって、属人化や記録のバラつきも抑制することができ、継続的な運用がしやすくなります。
計測・測定機器点検表に記録すべき主な基本情報と構成
計測機器の点検表は、日常的・定期的に機器を確認する中で異常の早期発見や事故の予防、計測精度維持を目的とした記録帳票です。以下のような項目を入れることで、点検作業の質と再現性が向上します。
| 項目 | 目的 |
|---|---|
| 基本情報 (機器名・識別番号) |
どの機器を点検したのかを特定するため、管理台帳と同様の項目を冒頭に配置 |
| 外観確認 |
|
| 動作確認 | 電源のON / OFF、操作ボタンの反応、ディスプレイ表示などの基本動作をチェック |
| ゼロ点確認 | ノギスやマイクロメーターなど、ゼロ点基準がある機器は誤差の蓄積を防ぐためにも毎回確認が必要 |
| 簡易精度確認 |
|
| 簡易清掃・使用後チェックの実施有無 |
|
| 点検日・点検者 |
|
点検表の設計では、1機器につき1枚のシートで記録する方式か、複数機器を一覧形式で1行ずつ記録していく方式のいずれかを用います。前者は記録の詳細を残したい場合、後者は現場で一括点検する場合に適しています。
記録のしやすさは最優先事項であるため、紙で運用する場合はチェックボックスや○×形式を活用し、記入の手間を最小限に抑える工夫が大切です。
また、異常が発見された際の対応内容を記載できるように、備考欄や処置欄をあらかじめ設けておくと、後続の修理・再点検にもスムーズに連携できます。
まとめ
計測機器の管理台帳と点検表は機器の基本情報や履歴、状態を体系的に記録します。そうすることで、精度維持や異常の早期発見、属人化防止に効果的に運用できます。
計測・測定機器の日常点検・校正管理における課題と解決策
計測・測定機器の正確性を維持するためには、日常的な点検と、定期的な校正を計画的に行う必要があります。
しかし、これらの管理業務には見落としや属人化など、現場で発生しやすい課題が多く潜んでいます。この章では、それらの典型的なリスクと、紙・Excel運用の限界、そしてその解決策となるデジタル管理の利点について解説します。
計測・測定機器管理で起こりがちなミスや属人化のリスク
まず最初に押さえておきたいのは、点検・校正業務のプロセスで起こりがちな人為的ミスと属人化の問題です。
たとえば、校正・点検の実施漏れはよくあるミスの一つです。スケジュール管理が不十分なままでは、定期校正のタイミングを過ぎてしまい、結果的に精度の保証がないまま使用されるケースが発生します。
また、データの記録ミスも頻繁に起こります。手書きや手入力での作業では、数値の転記ミスや記入漏れが発生しやすく、後から追跡できない原因にもなります。
さらに、点検・校正手順が明文化されておらず、ベテラン担当者の経験に頼っている状態では、属人化によって業務の再現性や引き継ぎ性が著しく低下します。特に担当者の不在時や退職後に、校正記録の意味や意図が読み取れないといったトラブルが起きやすくなります。
紙・Excel運用における課題と限界
上記のようなヒューマンエラーを回避するために、多くの企業では紙のチェックリストやExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトで作成した点検表を導入します。
特別なツールや導入コストも不要なので、これから点検業務を整えたい、ひとまず形式だけでも作っておきたい、という方にとってはフォーマットを参考にするだけでも、点検作業の全体像が掴めるはずです。
そこで本記事では、すぐに使える計測機器点検表の無料Excelテンプレートをご用意しています。印刷して紙で使うことも可能ですので、現場環境にあわせて自由にご活用ください。
なお、Excelによる運用をしばらく続けていくと、次のようなデメリットも見えてきます。
- 管理が煩雑:複数のファイルに情報が分散し、過去の履歴を確認するのに時間がかかる
- 記録ミスの多発:手書き・手入力による記入漏れや数字の間違いが発生しやすい
- 作業履歴が不明瞭:誰が・いつ・どこで点検したかが曖昧になり、責任の所在が不透明になる
- 承認フローが遅れる:上長の確認・承認に紙を回す必要があり、即時の対応ができない
- 保存・検索性が低い:紙の保存には物理的なスペースが必要で、紛失や劣化のリスクも高い
- セキュリティ管理が困難:アクセス権限のコントロールができず、情報漏洩リスクがある
このように、紙やExcelだけで運用を続けることは、一定規模以上の設備管理や精度保証が求められる現場では、むしろリスク要因となってしまいます。
CMMS活用による業務のデジタル化で得られるメリット
近年、注目されている点検手法がCMMSを活用したデジタル管理の導入です。これは、設備や測定機器の状態・点検履歴・校正記録などをクラウド上で一元管理できるシステムで、紙やExcelに代わる次世代の管理手法といえます。
CMMSを導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 情報の一元管理:すべてのデータがクラウドに集約され、必要な情報にすぐアクセス可能
- 記録の正確性向上:チェックリストや入力ガイドで記入漏れやミスを抑止
- 異常の予兆検知:履歴データを活用した傾向分析により、トラブルの兆候を事前に把握
- 業務の標準化と属人化防止:手順や作業記録をテンプレート化することで、誰でも同水準の業務を実施可能
- リアルタイム承認:点検終了と同時に上長へ通知を飛ばすなど、承認フローを迅速化
- 監査・ISO対応の強化:校正証明書・点検履歴がすぐに提示でき、外部監査にも対応しやすい
当社が提供するMONiPLATも、こうしたCMMSの要素を備えたクラウド型の設備保全プラットフォームです。点検や校正のスケジュール管理、記録の自動保存、リアルタイムの通知機能などを備えており、スマホやタブレットでも簡単に記録・管理できます。
特に、20設備まで無料で利用できるため、まずは一部の測定機器管理から試験導入することをおすすめします。
まとめ
計測機器の日常点検・校正管理は精度維持に不可欠ですが、紙やExcel運用では限界があります。CMMSなどの点検デジタルツールを導入することで、記録精度向上や共有効率化、監査対応強化が可能です。
計測機器管理台帳・点検表の活用で品質と信頼性を高めよう
計測機器は製品品質や安全性の根幹を支える重要な設備です。台帳や点検表を活用することで、測定精度の維持、トレーサビリティ確保、監査対応の強化が可能になります。
計測機器点検・校正のポイント
- 日常点検による異常の早期発見:外観・動作・ゼロ点などを日々確認し、破損や誤差の兆候を迅速に把握
- 校正記録による精度保証:標準器との比較測定で正確性を確認し、校正証明書を保管して監査にも対応
- 台帳管理による履歴一元化:管理番号や使用場所、校正周期などを記録し、記入漏れや属人化を防止
- デジタル管理による効率化:CMMSを活用することで、スケジュール管理や承認をリアルタイム化して業務を最適化
計測機器の信頼性を長期的に維持するには、日常点検と定期校正を計画的に実施し、記録を確実に残すことが不可欠です。まずはExcelテンプレートから始め、将来的にはデジタル管理を取り入れて効率化を進めましょう。
計測・測定機器の校正にはMONiPLATがおすすめ
紙やExcelでの管理を続けていく中で、情報の整理が難しい、記録のミスが多い、関係者と共有しづらい、といった課題を感じることもあるかもしれません。このようなお悩みに対して、点検・校正業務の効率化を後押しする選択肢のひとつとして、MONiPLATの活用をご検討ください。
MONiPLATは計測機器を含む設備の点検データをクラウド上で一元管理できるプラットフォームです。スマホやタブレットから簡単に記録でき、点検スケジュールの通知や、承認フローのデジタル化にも対応。紙やExcelで起こりがちな記入漏れ・情報共有の手間を減らしながら、日常業務の負担を軽減します。
今なら、20設備まで無料でお使いいただけるため、まずは小規模からでも気軽に導入可能です。Excelテンプレートなどで管理を始めた後、より効率化したくなった段階で切り替えるのもおすすめです。
点検業務の「次の一手」として、MONiPLATを選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部
デジタルソリューション部オペレーションマネージャー
藤田 勇哉(ふじた ゆうや)
計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。
