電気設備点検表の作り方と管理方法を徹底解説【無料Excelテンプレート付き】
更新日:
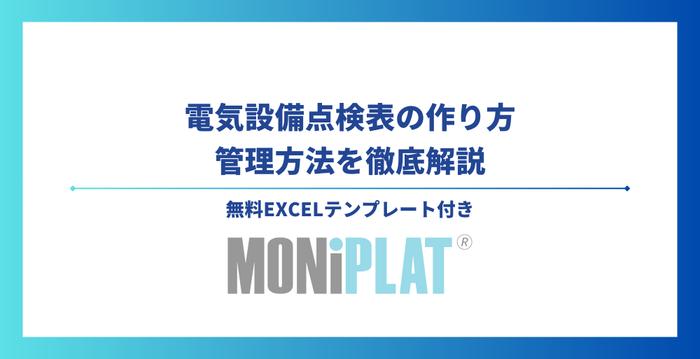
電気設備の点検は、事業の安全と継続に直結する重要な業務です。「どの設備を」「誰が」「どのような頻度で」点検すべきか分からない、といった悩みを抱える担当者は少なくないでしょう。
電気設備の劣化や不具合を放置すると停電・漏電・火災などの重大事故につながり、法的罰則や事業停止のリスクも伴います。特に高圧電気を扱う自家用電気工作物では、法令で定期点検が義務化されており、記録保存や報告の不備は企業の信用にも関わります。
本記事では、電気設備の種類から点検の頻度・項目・担当者の役割、点検表を活用するメリット、さらには点検業務DX化による業務効率化の方法まで、体系的に解説します。無料で使えるExcel点検表テンプレートもご用意しているので、自社に合った電気設備管理への第一歩を踏み出しましょう。
電気設備にはどのような種類があるのか?
電気設備とひとくちに言っても、その種類は多岐にわたります。どの設備を対象に点検・保守を行うかによって、必要な知識や対応方法、記録の管理方法も大きく変わってきます。
この章では、電気の供給経路に沿って分類される基本構成について解説します。それぞれの役割や分類の違いを理解することで、どのような電気設備にどのような点検や管理が必要かを明確にできるようになります。
電気設備の基本概要とそれぞれの役割
電気設備とは、発電から供給・利用に至るまでのあらゆる過程に関わる設備の総称です。私たちの生活や産業活動を支えるために、電気設備は段階ごとに役割が分かれており、それぞれに応じた点検や管理が求められます。
まずは、電気の流れに沿って代表的な電気設備の種類と役割を整理してみましょう。
| 種類 | 主な役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 発電設備 | 電気を作る |
|
| 送電設備 | 発電所から電気を遠くへ送る |
|
| 変電設備 | 高圧電気を段階的に低圧に変換する |
|
| 配電設備 | 地域や構内に電気を届ける |
|
| 構内設備 | 建物内で電気を利用する |
|
上記のように、電気設備は「作る→送る→変換→届ける→使う」という一連の流れに対応した構造となっており、それぞれに応じた点検基準が存在します。
これらの電気設備は法令上「電気工作物」と呼ばれ、設置者には一定の点検・管理義務が課されています。電気工作物は使用目的や規模によって大きく以下のように分類されます。
| 区分 | 電気工作物の種類 | 主な特徴 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 一般用 | 一般用電気工作物 | 600V以下の低圧で受電し、家庭や小規模な事業所で使用される電気設備 |
|
| 事業用 | 自家用電気工作物 | 出力や設置目的によって規制が一部緩和されており、保安規程の届出や主任技術者の選任が不要なケースもある |
|
| 上記以外の600Vを超える電圧で受電する中小規模発電事業設備のため電気主任技術者の選任が義務付け |
|
||
| 電気事業用電気工作物 | 電気事業者(一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業、特定規模電気事業者)が電気の供給を行うために設置する電気工作物 |
|
これらの分類に応じて、点検の頻度や担当者の資格要件も異なってきます。たとえば、一般用電気工作物では法定点検義務がないことが多い一方で、事業用電気工作物では厳密な点検と記録管理が法令で義務付けられています。
今後、点検表を活用して電気設備の保守を進めるのであれば、まずは対象設備がどの分類に該当するかを確認し、それぞれの設備に適した方法で記録・管理を行うことが重要です。
出典:[ 経済産業省/ 電気工作物の区分 ]
強電設備・弱電設備として使われる電気設備の紹介
電気設備はその電圧レベルや用途によって「強電設備」と「弱電設備」に大別されます。この分類を理解することで、どの設備にどのような点検や管理が必要か判断しやすくなります。
以下に、それぞれの特徴を整理しています。この分類は電気設備の保守や点検、さらには施工における必要資格にも関係するため、実務者にとって非常に重要な視点です。
| 分類 | 電圧帯の目安 | 主な用途 | 点検頻度 | 資格資格 |
|---|---|---|---|---|
| 強電設備 | おおよそ48V以上 | 電力の供給・変換・制御 | 法定点検対象が多い | 電気主任技術者、電気工事士 |
| 弱電設備 | おおよそ48V以下 | 情報通信、信号伝送・制御 | 任意点検が中心 | 無資格でも可 |
強電設備(電力系統)とは?
強電設備は、主に建物や設備に電力(エネルギー)を供給するための電気設備です。おおよそ48V以上の電圧で動作し、比較的高電力を消費するため、誤操作や劣化によって感電・火災・停電などのリスクが生じやすいという特徴があります。
また家庭・ビル・工場問わず、強電設備はあらゆる建物に設置されており、定期点検の対象にもなりやすいという特徴もあります。特に、以下の設備は高電圧を扱うことから、感電・火災・停止による業務影響のリスクが高いため、電気工事士や電気主任技術者などの有資格者による定期点検は必要不可欠です。
| 設備の種類 | 役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 電灯設備 | 電気を光に変換し、照明用途で使用 |
|
| 動力設備 | 電気を運動エネルギーに変換 |
|
| 受変電設備 | 高圧受電から低圧供給への変換 |
|
| 幹線設備 | 電力を各フロア・機器に配分 |
|
| 自家発電設備 | 建物内で電力を自己生成し、非常時やピークカットに対応 |
|
| 避雷設備 | 雷の直撃・誘導電流を逃がす |
|
弱電設備(情報通信系)とは?
弱電設備は、主に情報伝達や通信、制御などを担う低電圧の電気設備です。たとえば、建物内のLAN、電話、警報、セキュリティといったシステムが該当します。
一般に電圧は48V以下と低いので、感電リスクは低いですが、機器故障が業務に大きく影響するケースもあるため、安定稼働のためのメンテナンスが重要です。強電設備と比べて法的点検義務も少ないので、専門資格を持たなくてもメンテナンス実施可能な範囲は広いといえます。
| 分野 | 主な設備と役割 |
|---|---|
| 情報分野 | LAN、Wi-Fi、TV共聴、監視制御装置などオフィスやビルのネットワーク系統 |
| セキュリティ分野 | 防犯カメラ、入退室管理、電気錠などの監視・アクセス制御 |
| 音響・放送分野 | 公共施設・学校・商業施設内の館内放送、非常通報、ホール音響など |
| 消防・防災分野 | 法定設置が義務付けられている火災報知器、感知器、非常ベルなど |
まとめ
電気設備は発電から利用まで多様な種類があり、用途や電圧によって分類や点検基準が異なります。強電・弱電設備の特徴や必要資格を理解し、自社設備に適した保守体制を整えることが重要です。
電気設備の点検とは?基本概要を理解しよう
電気設備の安全運用には、定期的な点検と記録が欠かせません。特に、高圧以上の電気を扱う設備では、法令に基づく「電気保安点検」が義務付けられており、点検を怠ると重大事故や法的罰則につながる可能性があります。
この章では、電気設備点検に関する基本的な位置づけを理解するために、点検の重要性、点検種別ごとの点検頻度と実施内容、点検担当者の役割について解説します。自社の電気設備がどのような点検対象に該当し、誰がどの頻度でどのように点検すべきかを正しく理解しておきましょう。
電気設備の点検は義務?法令に基づく重要性を解説
電気設備の点検は任意ではなく、高圧(600V超)の電気を受電する自家用電気工作物を保有・使用する事業者には、電気事業法に基づいた定期点検の実施と記録管理が義務付けられています。
該当の法令に違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 電気事業法第115条:点検不備によって感電や火災などの事故が発生した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 電気事業法第118条:点検の未実施や保安規程違反などがあった場合、300万円以下の罰金
これらの法的責任は法人だけでなく、代表者個人にまで及ぶ可能性があります。そのため、点検の不備は安全上のリスクだけでなく、事業継続リスクや企業の信用低下にもつながります。
また法令遵守の観点だけでなく、人的被害・財産被害を未然に防ぐという意味でも、定期的な点検と適切な記録は不可欠です。点検を実施することで、以下のようなトラブルを未然に予防することにつながります。
- 配線の劣化による漏電・感電事故の防止
- 経年劣化した設備の火災リスクの回避
- 停電による業務停止の未然防止
- 異常発見時の迅速な対応による損失最小化
加えて、非常用発電機を設置する場合は電気事業法第42条だけでなく、建築基準法第12条に基づき非常用照明装置(電球や蛍光灯)・排煙設備を建築物の一部とし、消防法第17条の3の3に基づき消防設備およびその動力源となる発電機を対象として各法令に基づいた有識者による定期点検が義務付けられています。
電気設備の点検は単なる義務ではなく、事業を守るための最低限のリスク対策とも言えます。
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法第115条 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法第118条 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法第42条 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 建築基準法第12条 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 消防法第17条の3の3 ]
電気設備の点検頻度とそれぞれの点検項目
電気設備の点検は、電気保安点検と事業者が自主的に行う日常点検に分かれます。
電気保安点検は法令で義務付けられており、電気主任技術者または外部委任承認制度を利用した有資格者が実施します。以下の法令に基づき、事業用電気工作物の使用者は適切な点検と記録保存を行う義務があります。
- 電気事業法第42条第1項(自家用電気工作物の保安規程遵守義務)
- 電気事業法施行規則第53条(点検実施基準)
- 経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示)
一方で、日常点検は法定義務ではないものの、事故予防のために経済産業省が推奨している業務です。それぞれの点検種別を理解しておきましょう。
| 点検種別 | 実施頻度 | 主な実施者 | 主な目的 | 主な点検内容 |
|---|---|---|---|---|
| 月次点検 | 原則毎月1回 (条件により隔月または3か月ごと可) |
電気主任技術者または外部委任先 | 運転中の設備の状態確認と初期異常の発見 |
|
| 年次点検 | 毎年1回 (条件により3年1回可) |
同上 | 停電状態で内部まで詳細点検 |
|
| 臨時点検 | 異常・災害発生時 | 同上 | 事故や災害後の安全確認 |
|
| 電気事故対応 | 事故発生直後 | 同上 | 被害拡大防止と原因究明 |
|
| 日常点検 | 毎日・週次 | 事業担当者 | 異常の早期発見 |
|
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法第42条第1項 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法施行規則第53条 ]
出典:[ 経済産業省 / 経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示) ]
月次点検
電気設備の月次点検は原則として毎月1回、運転中の電気設備を対象に実施する法定点検です。日常点検では把握しきれない設備内部や運転状態の異常を早期に発見し、事故や故障を未然に防ぐために不可欠な工程です。
特に、自家用電気工作物を保有する事業者は、電気主任技術者または外部委任承認制度に基づく有資格者が実施する義務があります。なお、経済産業省告示第249号に規定された条件を満たす場合は、隔月や3か月に1回の点検に緩和できますが、その条件には設備の構造・容量・絶縁監視装置の有無などが細かく定められています。
月次点検の主な点検項目は以下の通りです。
- 配線や保安装置の外観確認(断線、ゆるみ、被覆損傷の有無)
- 電圧・電流測定による過負荷チェック
- 設備表面の劣化や亀裂の確認
- 異音や異臭の有無
また、月次点検は設備を停止せずに行うため、日常的な運用状態を確認できる一方で異常を発見した場合には即時の報告と適切な対応が求められます。さらに点検結果は報告書として記録し、3年間の保存が義務付けられています。
年次点検
電気設備の年次点検は毎年1回、設備を停電状態にして実施するもっとも重要な法定点検です。停電状態で点検を実施することで、運転中には確認できない設備内部の状態や経年劣化を直接調べることができます。
条件を満たすことで3年に1回まで頻度を延長することもできますが、その際も適切な代替措置や無停電点検の実施が必要です。
年次点検の主な点検項目は以下の通りです。
- 接地抵抗測定(事故電流を安全に大地へ逃がせるかの確認)
- 電路の絶縁抵抗測定(漏電や絶縁劣化の有無)
- 保護継電器試験(事故時の迅速遮断機能確認)
- 非常用予備発電装置試験(停電時の起動確認)
- 蓄電池試験(非常時に所定の時間動作できるか)
- 部分放電の有無や温度異常の確認
- 機器内部の清掃・注油
年次点検は停電を伴うため、生産ラインや業務への影響を最小化する計画が重要です。事前に日程や作業範囲を関係部署と共有し、必要に応じて仮設電源の手配なども検討しましょう。
臨時点検
電気設備の臨時点検は、定期点検のスケジュール外で設備に異常や外的要因によるリスクが発生した場合に実施される点検です。台風や落雷、大雪などの自然災害の直後や、通常運転では発生しない異音や振動が確認された場合に行われます。
また、梅雨時期や降灰地域など、環境要因でトラブルが発生しやすい時期に予防的に実施することもあります。
主な点検項目は以下の通りです。
- 外観・内部の損傷や変形の確認
- 動作状態の確認(起動・停止・制御系統の反応)
- 電圧・電流の異常値有無
- 気象災害後の絶縁状態確認
臨時点検においては、原因の特定と必要な修理の判断が迅速に求められます。特に、安全性が損なわれている場合には即座に使用停止や送電停止などの措置を取ることがあります。
電気事故対応
電気事故対応は、停電・漏電・機器焼損などの事故が発生した直後に行う緊急点検です。目的は被害の拡大防止と原因究明であり、速やかな現場到着と対応が求められます。電気主任技術者や委託先業者と連携して事故状況を正確に把握した上で応急処置を行い、復旧作業に移ります。
電気事故対応の主な点検項目は以下の通りです。
- 事故発生箇所と被害範囲の特定
- 損傷部品や焼損箇所の確認
- 関連機器の動作試験
- 再発防止のための改善策立案
事故対応後は詳細な事故報告書を作成し、原因と対策を関係者全員で共有することが重要です。再発防止のため、保安規程や点検計画の見直しも行いましょう。
日常点検(自主点検)
電気設備の日常点検は事業者が自主的に行う簡易的な点検です。法定義務はありませんが、異常の早期発見と予防保全に非常に効果的です。毎日、または週単位で実施されることが多く、常時運転している設備や重要設備では実施すべき点検と言えます。
主な点検項目は以下の通りです。
- 外観確認(損傷・汚れ・腐食の有無)
- スイッチやランプなどの動作確認
- 異常音・異臭の有無
- 過熱や異常振動の有無
- 周辺環境の安全確認(可燃物の有無、通風の確保など)
点検の結果、異常が見つかった場合はそのまま放置しないで即座に電気主任技術者や保安担当者へ報告し、必要に応じて臨時点検へと移行します。日々の目視点検の中でも小さな異常に気付くことで、大きな事故や設備停止を防ぐことができます。
電気設備点検の実施担当者は誰?役割と責任について
| 電気工作物の種類 | 点検実施担当者 | 法的根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般用電気工作物 | 一般従業員でも可 | 特段の規定なし | 住宅・小規模店舗等 (600V以下で受電) |
| 事業用電気工作物 | 電気主任技術者必須 | 電気事業法第43条第1項 |
|
| 自家用電気工作物 | 電気主任技術者必須 (外部委託可) |
電気事業法第43条第1項 |
|
| 小規模事業用電気工作物 | 設置者が実施 (資格不要) |
電気事業法施行規則第52条の2 |
|
電気設備の点検は、その設備の種類や用途に応じて実施できる担当者が法律で定められています。特に、事業用電気工作物においては、電気事業法第43条第1項に基づき「電気主任技術者」を選任する義務があり、その人物が定期点検や保守計画、異常発生時の対応を担います。
一方で、一般用電気工作物や小規模事業用電気工作物の一部については、必ずしも有資格者による点検を義務付けられていません。しかし、専門知識の不足による見落としや誤判断が事故につながる可能性があるため、実務上は有資格者または経験者による点検が推奨されます。
自家用電気工作物を保有する事業所においては、事業所に電気主任技術者を常駐させるのが原則ですが、経済産業省の「外部委託承認制度」を利用することで、外部の有資格業者に業務を委託することが可能です。この場合でも、最終的な保安責任は事業者側にあり、委託先は点検結果の正確な報告と改善提案を行う義務があります。
電気主任技術者や外部委託先は以下のような責任を負います。
- 定期点検の計画立案と実施
- 点検結果の記録と保存(法定保存期間を遵守)
- 不具合発見時の迅速な修繕・改善措置の提案
- 電気事故発生時の応急対応と原因究明
- 再発防止策の策定と実行
点検の実施担当者の要件は設備の種別と規模によって異なります。特に、高圧以上の電気を扱う事業用・自家用設備においては法令遵守と安全確保のため、必ず有資格者が点検に関与する体制を整えることが不可欠です。
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法第43条第1項 ]
出典:[ e-Gov法令検索 / 電気事業法施行規則第52条の2 ]
まとめ
電気設備の点検は安全確保と法令遵守のため不可欠です。設備の種類や規模に応じた点検頻度・方法・担当者を正しく理解し、計画的な点検と記録で事故やトラブルを未然に防ぎましょう。
電気設備の点検表とは?点検業務スマート化への移行
電気設備の点検表は設備機器の状態を正確に把握し、法令遵守や事故防止のための記録を残す重要なツールです。紙やExcelで作成する従来の方法でも一定の管理は可能ですが、近年ではDX化による点検業務の効率化が注目されています。
この章では、まず点検表を活用することで得られるメリットと点検表に記載すべき必須項目を解説します。そのうえで、従来の点検表の限界と点検業務のデジタル化による利点を比較し、より効果的な運用方法を紹介します。
点検表を活用するメリットとテンプレート記載項目
電気設備の点検業務において、点検表は安全性の確保と作業効率の向上を両立する重要なツールです。紙や口頭での確認だけでは記録漏れや記載ミスが発生しやすく、法令遵守や事故防止の観点からもリスクが高まります。
点検表を活用する主なメリットは以下の通りです。
- 安全性の確保:定められた点検項目を網羅的に確認でき、感電や火災などの重大事故を防止
- トラブルの早期発見:設備の劣化や異常を初期段階で把握でき、事故を未然に防止
- 点検作業の効率化:項目が体系化されているため、作業の標準化・時短化が可能
- コスト削減:故障を未然に防ぐことで、修理や設備更新にかかる費用を低減
- 記録の整備と活用:設備の状態変化を記録し、将来の点検計画や保全計画に反映できる
- 法令遵守の証明:電気事業法や労働安全衛生法など、法定点検を実施・証明できる
- 顧客・社内からの信頼性向上:点検実績を示すことで、安全管理体制の信頼性が高まる
これらのメリットを最大限活かすためには、必要項目が適切に整理された点検表テンプレートを用意することが重要です。以下は、電気設備の点検表に盛り込むべき代表的な項目例です。
| 区分 | 項目 | 内容例 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 設備名 | 点検対象の名称(例:受変電設備、分電盤) |
| 点検日 | 点検を実施した日付 | |
| 担当部署、担当者名 | 点検を行った部署と担当者氏名 | |
| 点検項目 | 外観点検 | 破損・変色・腐食・汚れの有無を確認 |
| 電線・ケーブル | 損傷、断線、絶縁の状態を確認 | |
| 接続部 | ゆるみ、接触不良の有無を確認 | |
| 遮断器の動作 | 適正に動作するか、トリップテストの実施 | |
| 漏電の有無 | 漏電検出器や測定器による確認 | |
| 温度測定 | 赤外線温度計などで異常発熱がないか確認 | |
| 異常音・異臭 | モーター音や焦げ臭などの有無を確認 | |
| 判定・記録 | 合否判定 | 基準に基づき合格・不合格を記載 |
| 備考欄 | 不合格時の修理内容・改善指示などを記載 |
現場や設備の種類によって追加すべき項目は異なりますが、法令改正や設備更新のタイミングで見直すことが重要です。これにより、常に最新の基準で点検を行い、安全性と効率性を高い水準で維持できます。
本記事では、電気設備点検表のExcelテンプレートをご用意しておりますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
点検業務をDX化することによるメリット
近年、あらゆる業務で進むDX(デジタルトランスフォーメーション)は電気設備の点検業務にも活用することができます。従来の紙や表計算ソフトを用いた管理方法は、手軽さこそあるものの、記録漏れ・情報共有の遅延・管理の非効率化といった課題を抱えています。
紙・Excelによる点検表管理の課題と点検業務をデジタル化するメリット、この2つの視点から、なぜ今DX化が必要なのかを詳しく見ていきましょう。
| 従来の点検表 | 設備保全管理システム |
|---|---|
| 紙やExcelでバラバラ管理 | クラウドで一元管理 |
| 入力・転記ミスが発生 | 標準化された入力フォーム |
| データ共有に時間がかかる | リアルタイム共有 |
| 過去データの検索が困難 | 簡単に検索・分析が可能 |
| セキュリティ面で脆弱 | 権限設定・暗号化で安全 |
紙・Excelを用いた設備の点検表管理に潜む課題と限界
紙やExcelを用いた点検表は、初期費用がかからず誰でも簡単に使い始められるというメリットがあります。しかし、実際の運用では以下のような課題が浮き彫りになります。
- 記録ミス・入力漏れ:手書きや手入力による誤記や記録漏れが発生しやすく、精度が安定しない
- 作業者の特定が困難:誰が・いつ・どのように点検したか明確に残らないケースがある
- 管理・保存の手間:紙は劣化・紛失のリスクがあり、Excelもファイルのバージョン管理が複雑
- 情報共有の遅延:紙やメール添付での共有はタイムラグが発生し、迅速な対応が困難
- セキュリティの脆弱性:紙の紛失や無断持ち出しやExcelのパスワード漏洩など、情報漏洩リスクが高い
上記のような課題は、経済産業省や業界団体のDX推進ガイドラインでも指摘されており、特に、記録の正確性確保と情報の即時共有性は電気保安の現場で重要な評価ポイントとされています。
設備保全管理システムを用いることで得られるメリット
設備保全管理システムなどの点検業務のデジタル管理ツールは、点検業務の効率化と品質向上を同時に実現します。点検業務をDX化することで、以下のようなメリットを得られます。
- 記録の一元管理:点検結果や設備履歴をクラウド上で集中管理し、必要な情報に即時アクセス可能
- 記録精度の向上:入力フォームの標準化により、記録ミスや漏れを防止
- リアルタイム共有:点検データを即座に関係者と共有でき、異常発見時も迅速な対応が可能
- 点検プロセスの可視化:スケジュール・進捗・結果を一目で把握でき、作業の属人化を防ぐ
- 改善サイクルの促進:過去データ分析により、点検計画や保守方針の最適化が可能
- ISO9001や法令遵守への対応:トレーサビリティ確保や記録保存要件を満たしやすくなる
当社が展開するMONiPLATでも、多くの企業が点検業務のデジタル化によってさまざまな成果を上げています。詳細は以下の導入事例をご覧ください。
まとめ
点検表は法令遵守や事故防止に不可欠で、DX化により精度・効率・共有性が大幅に向上します。適切な項目設定とシステム活用で安全管理を強化しましょう。
電気設備の点検で安全性と効率性を高めて事業リスクを防ごう
電気設備の点検は事業の安全確保と法令遵守、事故防止のために欠かせない活動です。適切な管理体制を整えることで、設備の安定稼働とコスト削減を両立できます。
電気設備点検のポイント
- 設備分類ごとの適正点検:強電・弱電や法区分を踏まえ、対象設備に応じた点検頻度・方法で実施
- 点検表テンプレートの活用:必要項目を網羅した点検フォーマットで記録漏れや作業のばらつきを防止
- 記録の蓄積と分析:異常や劣化の傾向を早期に把握し、計画的な保全や更新に活用
- DX化による効率化と精度向上:スマホ・タブレット入力で即時共有し、承認や改善サイクルを加速
日常的な管理から法定点検まで、一貫した点検体制を構築することが安全性と事業継続の鍵です。Excelテンプレートや点検業務のDXツールを活用し、現場の点検品質と効率を同時に向上させましょう。
さまざまな電気設備の点検にはMONiPLATがおすすめ
電気設備の点検を効率化して記録や管理を一元化したいと考えている方には、当社の設備管理システムMONiPLATの活用がおすすめです。MONiPLATのTBM機能であれば、さまざまな電気設備を含む最大20設備まで無料で利用できます。
スマホやタブレットから現場で直接点検結果を入力でき、クラウド上で即座に共有。点検スケジュールの管理や担当者への通知機能も備えているため、作業漏れや記録の遅延を防げます。また電気設備だけでなく、建築・機械・安全設備などの点検も同じプラットフォーム上で管理できるので、現場全体の保全管理状況を把握しやすくなります。
自社の電気主任技術者だけでなく、外部委託先の有資格業者にも無理なく点検業務のDX化を試していただく場合にも最適です。無料枠を活用して、自社の点検フローに合うかどうかをぜひお試しください。
#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部
デジタルソリューション部オペレーションマネージャー
藤田 勇哉(ふじた ゆうや)
計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。
